ブログ blog page
お金で世界が見えてくる!
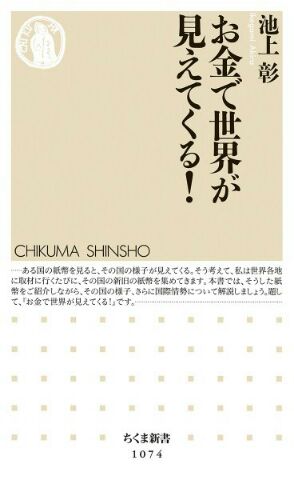
池上彰著(ちくま新書)
◎はじめに
お金は、なぜお金なのか、みんながお金と思っているから。
第1章 奇妙な数字、奇妙な政治
ーーミャンマー
真の独立が獲得できなかったことに失望したアウンサンは、今度はイギリスと連絡を取り、日本支配に対する反乱を起こし、日本軍を追い出しました。
このしたたかな戦略により、第二次世界大戦後はイギリスからの独立を果たします。
しかし、独立寸前、政治テロによって殺害されてしまったのです。アウンサン32歳でした。
第2章 デノミに失敗した北朝鮮
ーー北朝鮮
北朝鮮の公式の伝記では、金日成は、朝鮮半島が日本の支配下にあった1930年代から40年代にかけて、抗日遊撃隊率いて朝鮮半島で日本軍と戦って戦果を挙げたということになっています。ところが、旧満州で活動中、日本軍に追われてソ連に逃げ込み、ソ連軍大尉として訓練を受けていました。
第3章 独裁者が倒された後の紙幣
ーーリビア/イラク
国内に監視網を張り巡らし、住民を抑圧して盤石の独裁政治を確立していたと思われていたカダフィ政権も、あっという間に崩壊してしまったのです。独裁政治の脆弱さを痛感します。
第4章 ホメイニが睨む紙幣
ーーイラン
しかし、イギリスやアメリカの怒りを買ったモサデク首相は、アメリカのCIA(中央情報局)が仕組んだクーデターによって失脚します。
その後、パーレビ国王の下で親米国家となったイランでは貧富の格差が拡大。国民の不満が爆発し、ホメイニ師を指導者とするイラン革命が勃発したのです。
第5章 ユーロ危機を招いたギリシャ
ーーヨーロッパ
ユーロには構造的な問題が2つあります。
そのひとつは、ユーロ加盟国の金融政策は欧州中央銀行が決めるのに対して、財政政策は各国の政府に任されていることです。
…
もうひとつの問題は、為替相場の変動で景気回復という方法がとれないことです。
第6章 紙幣は2種類
ーーボスニア・ヘルツエゴビナ
「1から7つの共和国」
ーー「1つの国家、2つの文字、3つの宗教、4つの言語、5つに民族、6つの共和国、7つの国境」
第7章 難民キャンプで通用する紙幣は?
ーーシリア/ヨルダン
同じシーア派であるイランの政権が、アサド政権を支援。さらに、シリアの西側のレバノンを拠点とするシーア派過激組織ヒズボラ(神の党)も、アサド政権支援に駆けつけます。スンニ派とシーア派の代理戦争のような状態になってしまったのです。
第8章 偽造に悩むアメリカドル
ーーアメリカ
「世界のお金」とは、国際貿易で決済に使われる通貨のこと。第二次世界大戦前まではイギリスのポンドが「世界のお金」でしいた。
しかし、戦争でイギリスの国力は衰え、先進国で唯一戦場にならなかったアメリカに、世界の富が集中したことで、アメリカがイギリスに取って代わったのです。
第9章 日本の援助が紙幣の図柄に
ーー日本のODA
バングラデシュは、かつては東パキスタンでした。1947年、イギリス領インドが独立する際、イスラム教徒が多く住む東西の領域が、ひとつのパキスタンとして独立したのです。
国家としてはひとつでしたが、間にインドを挟んで遠く離れていること、東パキスタンはベンガル人が主体で、西パキスタンとは民族や言語が異なることから、1971年3月に独立を宣言。これを認めなかった西パキスタンと戦争になりました。
結局、インドの支援を受けた東パキスタンが勝利し、12月に正式に独立を宣言。「ベンガル人の国」=バングラデシュになりました。
第10章 南アフリカとマンデラの死去
ーー南アフリカ
日本と韓国、台湾は、国際社会の流れに従わずに南アフリカとの貿易を続けたため、名誉白人の地位を与えられ、白人施設を利用することが許されました。まことに不名誉なことでした。
第11章 円から日本社会が見えてくる
ーー日本
たとえば金利を低くしようとすれば、紙幣の発行量を多くします。金利とは、いわば「お金の値段」。世の中の紙幣の量が多くなれば、需要と供給の関係で金利は下がります。
では、紙幣の発行量を多くするには、どうしたらいいのか。一般の銀行は、日本政府が発行している国債を大量に買い込んでいます。この国債を日本銀行が買い上げます。すると、その分だけ、日本銀行券が世の中に出回る、というわけです。
この記事を表示
合同会社とその利用上の留意点
記事全文を読む
正義ならば勝て
記事全文を読む
ミキ健康セミナー
記事全文を読む
モンテスキュー
記事全文を読む
小規模企業優遇政策
記事全文を読む
平成26年度税制改正
記事全文を読む
平成26年度税制改正
記事全文を読む
小規模宅地特例と要介護認定
記事全文を読む
和平之橋
記事全文を読む
顧明遠先生
記事全文を読む
平和の架け橋
記事全文を読む
繰越控除できない
記事全文を読む
移転価格についての留意点
記事全文を読む
ホームリーブ費用
記事全文を読む
いつも先生は…
記事全文を読む
吝嗇
記事全文を読む
学べ!
記事全文を読む
改革・開放の父
記事全文を読む