ブログ blog page
2020.8.30-4(2)
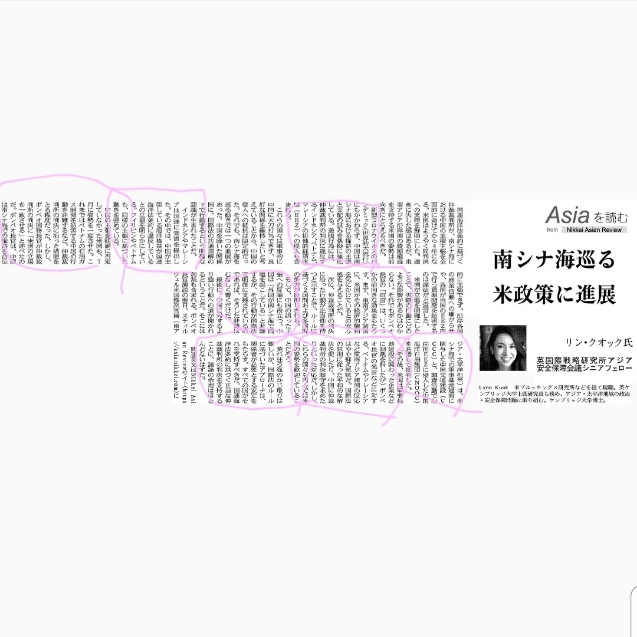
???????????????????????
【Asiaを読む】南シナ海巡る米政策に進展
英国際戦略研究所アジア安全保障会議シニアフェロー
リン・クオック氏
日本経済新聞 朝刊 オピニオン(8ページ)
2020/8/29 2:00
国連海洋法条約に基づく仲裁裁判所が、南シナ海における中国の主権主張を全面的に退けてから4年になる。米国はようやく同判決への支持を鮮明にした。遅きに失した感はあるが、東南アジア沿岸国の資源権益を支持する米国の姿勢は前向きにとらえるべきだ。
新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)にもかかわらず、中国は南シナ海における権益の主張と支配の試みを執拗に強化している。逸脱行為には、仲裁裁判所の判決に違反するインドネシア、ベトナム、マレーシアの排他的経済水域(EEZ)への侵入も含まれる。
これらの国々は軍事的に中国に太刀打ちできず、良好な関係を維持したいと考えていることから、中国の侵入への抵抗は限定的だった。それでも、南シナ海を巡る動きでは一つの進展があった。中国を除いた関係国に、国際法の共通理解の下で行動するという明確な認識が生まれたことだ。
インドネシアやマレーシアは国連に覚書を提出した。その中では、中国が主張している海洋権益が国連海洋法条約に違反しているとの立場を明らかにしている。フィリピンやベトナムも、同様の主張に基づいた動きを強めている。
中国の主張を明確に否定していなかった米国も、7月に姿勢を一変させた。これまではベトナムの石油ガス開発を妨害する中国の行動を非難するなど、仲裁裁判所の判決に沿った措置をとる程度だった。しかし、ポンペオ国務長官が仲裁裁判所の判決に「米国の立場を一致させる」と述べたのだ。ポンペオ長官は、中国は南シナ海での権益を合法的に主張できず、沿岸各国の漁業活動への嫌がらせや、各国が自国のEEZ内で行う資源開発を妨害するのは違法だと宣言した。
米国が立場を明確にしたことで、実際の行動にどのような影響があるかはわからない。それでもポンペオ長官の「宣言」は、いくつかの前向きな効果をもたらす。まず、東南アジア諸国に、米国がその経済的権利を気にかけているとの安心感を与えることだ。
◇◇
次に、仲裁裁判所の判決に沿った行動が正当性を持つと示すことで、ルールに基づく2国間および多国間の努力が後押しされる。
そして、中国の誤った主張への反論にも役立つ。中国は「外国が南シナ海で問題を起こしている」と非難するが、その行動が国際法で明確に支持されているのであれば、そうした非難はむなしく響くだけだ。
最後に、中国に対するより強い行動への道が開かれるということだ。そこには制裁も含まれる。ポンペオ長官演説の翌日、スティルウェル米国務次官補(東アジア・太平洋担当)は、南シナ海での軍事基地建設に関与した中国交通建設(CCCC)と、調査活動で沿岸国EEZに侵入した中国海洋石油集団(CNOOC)を名指しで批判した。
(その後、米国は軍事基地建設に関わった企業などに制裁を科したが)ポンペオ長官の発言などに対する、ベトナムやマレーシアなど東南アジア諸国の反応はやや抑え気味だ。国際法の原則に従った平和的な解決を促したり、中国に仲裁裁判所の判決順守を求めたりといった対応だ。しかし、これらの国々も内心では米国の姿勢を歓迎していることだろう。
荒れ狂う海のかじ取りは難しいが、国際法のルールに基づいたアプローチは、関係者が必要とする安定をもたらす。すべての国がそれを支持すべきだ。国連海洋法条約に基づく正当な仲裁裁判所の判決を支持することに、議論の余地はほとんどないはずだ。
関連英文はNikkei Asian Reviewサイト(https://asia.nikkei.com)に
Lynn Kuok 米ブルッキングス研究所などを経て現職。英ケンブリッジ大学上席研究員も務め、アジア・太平洋地域の政治・安全保障問題に取り組む。ケンブリッジ大学博士。
●カギ握るのはASEAN
日本経済新聞 朝刊 オピニオン(8ページ)
2020/8/29 2:00
海洋権益を巡る駆け引きは大国のエゴのぶつかり合いだ。国連海洋法条約に参加する中国が、南シナ海全域が自国の主権内とする立場を同条約に沿って退けた仲裁裁判決を、無視しただけではない。判決を支持し、中国の主張を「完全に不法」と断じた米国は、実は同条約を批准していない。深海の資源開発を自国に有利に進めるためだ。
米国は南シナ海で軍事拠点建設に関わった中国企業に禁輸措置を科したが、圧力を強めても中国の実効支配が覆る可能性は低い。中国は東南アジア諸国連合(ASEAN)と、同海域での各国の活動を法的に規制する「行動規範(COC)」の策定を急ぎ、自らに有利なよう国際ルールを上書きしようともくろむ。その意味でもカギを握るのはASEANだ。
(アジア総局長 高橋徹)