ブログ blog page
2017.1.30
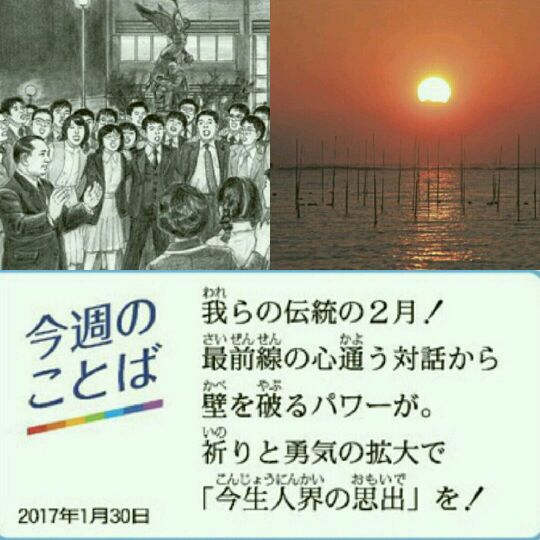
旧四月会の亡霊に翻弄されている自民党は何処も分裂気味、右傾化しかない維新は全滅、迷走の民進は全く元気なし、元祖日本版ポピュリズム共産には絶対に負けられないと、婦人部と青年部に火が付き、壮年部はあとから付いていき、最後は公明の大逆転勝利!?
良い意味悪い意味、宗教を怒らせたら恐いのだ!ざまー見ろ!でも四月会、共産党、マスコミとの戦いが、今後の米中韓の鍵を握る公明党のベースになっていくものと思います。
定数4減の中、敢えて2議席増に挑戦し、青年部への厳しい訓練にもなり、その意味でも、北九州大勝利は本当に良かったです♪厳しければ厳しかったほど、勝ち越えた醍醐味は我が身の福運となります。お願いした方へのお礼状と、都議選の電話した方へ自己紹介状、合わせて100枚以上を早速数日中に発送します!
今週2月4日土曜日は大分交流へ、JRとレンタカーで夫婦日帰りで行くことにしています。目標は10件!昨年(参)で反応のとても良かった◎印の税理士を回ります!
??????????????????
来月の月末金曜日から始まる「プレミアムフライデー」、“雇用の最先端”を自負するうちの事務所も早速導入することにしました。
皆に言ったら妹「たぶん所長の事だから、“する”と言うだろうと思っていました」。
私「所長自らあまり仕事したくないだけ」
(笑)
尤も2月下旬は確定申告の真っ最中で、私も既に予定がありますので、現実には無理だと思いますが、「取り合えず各人で取れる人は取って!3月からは完全実施!」
うちの事務所はかつて努力しても努力しても、売上が上がるどころか、下がり続けた“お陰で”、雇用助成金を6年間貰い続けた“名残”で、今は私も含め全員「完全週休3日制」となっています。まさに “雇用の最先端” !何がいい方向に向かわせるか分かりません。
経営も人生も「試練に遭遇してからが本当の勝負」だと思います。
??????????????????
真言天台勝劣事 134ページ?
第四章真言が七重八重劣る理由を示す
文永七年 四十九歳御作?
◎次に無量義経に云く「次に方等十二部経摩訶(まか)般若(はんにゃ)華厳(けごん)海空(かいくう)を説く」云云、
<通解>
無量義経に云く「次に方等十二部経摩訶般若華厳海空を説く」云云、
◎又云く「真実甚深(じんじん)甚深甚深なり」云云、
<通解>
又云く「真実甚深甚深甚深なり」云云、
◎此の文の心は無量義経は諸経の中に勝れて甚深の中にも猶甚深なり 然れども法華の序分(じょぶん)にして機もいまだなま(不熱)しき故に正説の法華には劣るなり此其二、
<通解>
此の文の心は無量義経は諸経の中に勝れて甚深の中にも猶甚深なり然れども法華の序分にして機もいまだなましき故に正説の法華には劣るなり
<解説>
『教えの高低浅深を明らかにする』
初めの文は無量義経説法品第二の文で、仏が菩提樹の下で悟って以来、説いてきた教えの高低浅深を明らかにする中の一節である。
『四諦〜大乗無量義経』
そこには、初めに四諦の法門を説いた後、十二因縁の法門を説き、次いで、方等十二部経、摩訶般若、華厳海空を説き、そして今、大乗無量義経を説法するという次第で説いてきたことが述べられている。
『小乗教』
ここで、四諦、十二因縁の法門は小乗教であるので、大聖人はこれを外して引用されたのである。
『教法の高低浅深』
この順序が説時でないことは、最初に説かれた華厳経が般若よりあとに挙げられていることから明らかで、そこからこれは、教法の高低浅深の順を示していることが分かるのである。
『方等部 般若部 華厳部』
方等十二部経は方等部に属する大乗経典の全てであり、摩訶般若は般若部、華厳海空は華厳部をさしている。
『大乗無量義経を説く』
これらの諸経の後に、大乗無量義経を説くと述べているから、無量義経が方等・般若・華厳より高い経であることは明らかとなる。
『真実甚深、甚深甚深』
次の文は無量義経十功徳品第三の文で、大荘厳菩薩が仏の説いた無量義経を微妙甚深、無上大乗、真実甚深、甚深甚深、と形容して賛嘆しているところである。
『方等・般若・華厳より高い』
以上の二つの問から、無量義経が方等・般若・華厳より高い教えとされていることが明らかとなる。
『法華経を説くための開経』
しかし、無量義経と法華経の関係については、無量義経が法華経を説くための開経であり序分であること、この経を聞く衆生の機根もまだ熟していないことから、正宗分の法華経には劣ると位置づけられている。
『法華経の次に位置』
以上によって、無量義経が法華経の次に位置し、諸大乗経に勝ることを明白にされたのである。