ブログ blog page
その律儀な気性にお目を
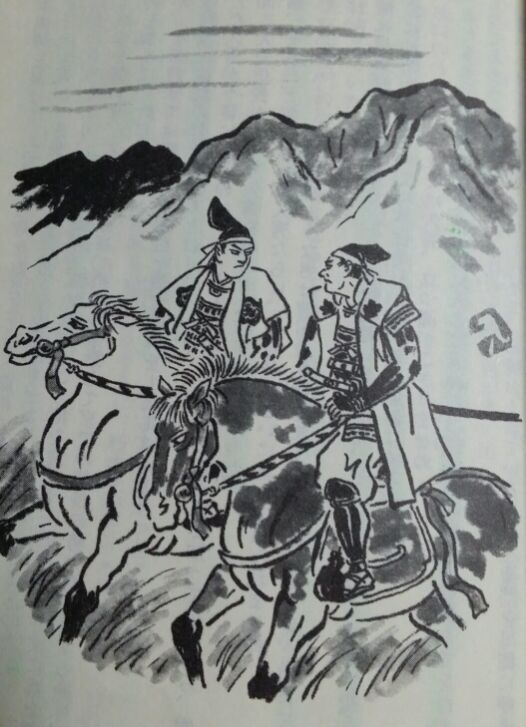
第5巻 うず潮の巻
◎天下布武
「ほんに、織田の殿さまは果報なお方じゃ」
老若男女のそうしたささやきを当の信長もまた群衆にまじってのどかな表情で聞いて歩いていた。
つねに民衆の声を聞くーーそれが信長の堅い政治の信念だった。
◎不如帰(ほととぎす)
これが二児の母……ではなくて、すでに三度目の子をみごもった母親の姿であろうか。まだ二十にも見えない。
……
その母に似た茶々姫の上にはどのような運命が待っているのであろうか?
……
長政は二十六歳。
浅井、朝倉の交わりはいわばお互いが、お互いを必要としたときの攻守同盟であり、それは時世の変化とともに改めて考え直さるべきものに想えた。
みやびと武断は、同じところにはなかったのだ。とすればこの乱世には武断の方が……
「……よって浅井、織田両家の交わりはこれまで。誓書返却のうえ、改めてお館に一矢(いっし)お酬い申すとの口上でござりまする」
木下藤吉郎が、秀吉と名を改めたのは、伊勢の北畠攻めのおり、すすんで苦難を引き受ける勇気を信長に賞され、
「ーー朝比奈三郎義秀にも比すべきもの」
と言われた。その義秀を秀義と逆にした名乗りであった。そしてその後「義」の字が将軍義昭の「義」であることから、はばかりありとして「吉」に改めた。
「猿! 浅井めが寝返ったぞ」
「……事実その中に謎があったとしても、それに頼るは油断のもと。ただ誓書を突き返さねば心が済まぬという……その律儀な気性にお目をとめられませ」
「浜松どのばかりに頼めませぬ。この秀吉にしんがり仰せつけ下さりませ」
(愛(う)い奴め)
この猿だけは、危険がせまると、必ずそれを買ってでる。勇気というよりも、それはむしろ絶えざる自分への試練であり運試しのようでもあった。
退き戦ほどむずかしいものはない。
「時には毒草こそ薬になる。こなたは得難い毒草ゆえ、そっとしておく。よいか、この信長に油断あらばいつでも本性をあらわして首を盗みにくるがよい」