ブログ blog page
邪馬台国は瀬高に!
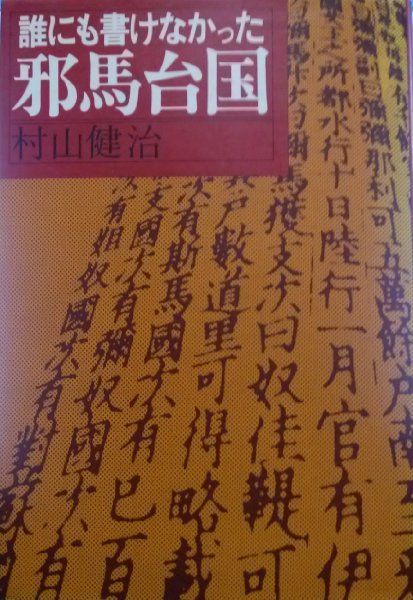
誰にも書けなかった「邪馬台国」
村山健治著
◎序章 自転車で探した邪馬台国
詩人北原白秋は、ふるさとの筑後山門をこう歌った。
山門はも うまし耶馬台(やまと)
いにしへの 卑弥呼が国
水清く、野の広らを
稲豊(ゆた)に 酒を醸(かも)して
菜は多(さわ)に 油しぼりて
幸(さちお)ふや 潟の貢と 珍(うづ)の貝
ま珠。照る鮨(はた)。
見さくるや童(わらべ)が眉に、
霞引く女山(ぞやま)。清水。
朝光(あさかげ)よ雲居立ち立ち
夕光(ゆうかげ)よ潮(しお)満ち満つ
げにここは耶馬台(やまと)の国、
不知火や筑紫潟、
我が郷(さと)は義しや。
「なしけん、そげん邪馬台国にとっ憑かれたかんも」
「産女谷(うぐめだに)に行っちゃでけんばん。あすこに行くと、ウンダカショにとり憑かれるけんのう」
「これはのう、昔の昔の大昔からの言い伝えじゃけん、忘れんごつしとかやんばん」
平野部に限っていうと、微高地からしか遺物は出ないのである。なぜそうなのか。
「郷土史家は偏狭な郷土愛のために、歪んだ目で郷土の過去を見る」
ーーしかし現在では、山門郡だけという狭義なものでなく、八女郡南部から熊本県の菊池郡あたりまでが、三世紀の邪馬台国であり、その王城の地が山門郡瀬高町の大塚だった、というふうに変わってきている。
「どうにも生活できんごとなりましたけん、別れましょう。私は子供ば連れて家を出ます」
「別れてから、どうやって生きていく」
「どうにもならんごつなったら、ボロ買いでもします」
「これだ」
「ボロ買いなら、おれがしてもよか……」
【先土器時代の区分表】
新石器時代
↑
中石器時代 1万年前
↑
旧石器時代
(上部) 4万年前 尖頭器 細石器
↑
(中部) 8万年前 ナイフ形石器 刃器
↑
(下部) 60万年前 敲打器
住居跡には必ず湧水地がある。川水は増水で汚れたりして、飲用に適さないためであろう。旧石器や縄文の頃だと、湧水地に鳥獣が集まるのを取ったりもしたと考えられるから、その近くに居住することは利点が大きかったはずである。
青磁とは磁器、それも高級品である。青磁は宋の時代に中国で作られた。青磁は高価なものである。青磁が出土するというのは、その場所に強大な権力や富があったことを意味する。まして、中国製の古い青磁が出てくれば、古い時代にそれだけの力がその土地にあった、という証拠となる。
洪積世初期(約六十万年前)、樺太、日本、台湾は大陸と地つづきで、東シナ海は陸地で、日本海の中心部は大きな湖だったという。第三氷河期(約二十万年前)には、陸地がだいぶ後退したが、樺太から九州までは長い地つづきで、九州は朝鮮と、樺太は沿海州と、まだつながっていた。有明海などももちろんありは、しなかった。
旧石器時代に阿蘇山が大噴火でできた。そのとき、陸地の一部が陥没して海となったのが、今の有明海だといわれている。
「人間ちゅうものは、真面目に生きとれば、天の助けがある。ちょうどよかときに、よか仕事が転がり込んできたたい。ま、それもこれも遺跡と付き合うたおかげばい」
「付き合わんだったら、もっと楽に生きられたと思いますよ」
私の入院生活は二年間つづくのだが、この期間が、家内にとっては一番安穏な日々であったろうと思う。