ブログ blog page
山東半島
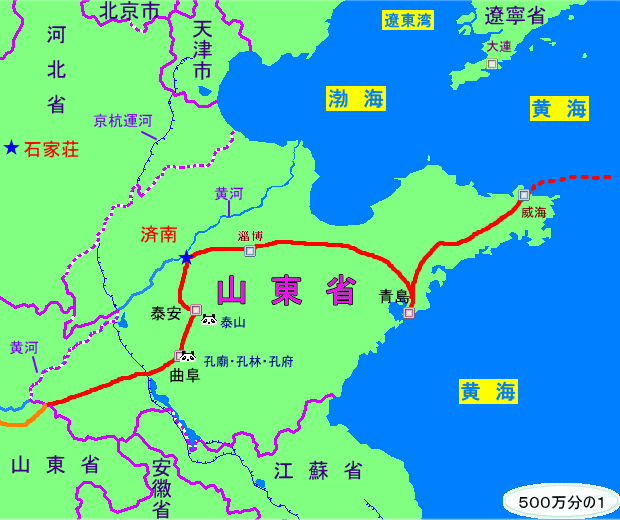
項羽と劉邦」(下)2
◎半ば渡る
この大陸は、春秋戦国時に諸子百家がむらがり出て、一大思想時代を経験している。
知識人のことを、
「生」
と尊称する。
「儒者なら、こういう事態になれば予測がつかなくなるのです。国や世はかくあるべしという理想を最初にえがき、物事をそれへ当てはめてゆこうとしますから」
この夜、韓信は上流の狭隘(きょうあい)部を土嚢でせきとめさせた。…しかし一晩保つ程度であるにせよ、下流へ流れる水量が半減した。
下流の一点に、韓信が立っている。
「韓信みずからが寄せてきた」
「おどろけ。おびえよ」
…ふたたび河にむかって崩れるようにして退却しはじめた。…韓信をあなどりきっていた竜且は簡単にかかった。
「客よ」
「わしがいったとおりではないか。韓信の臆病はいまにはじまったことではないのだ」
「一挙に韓信を討ちとれ」
韓信はさらに逃げ、敵を上陸させた。敵が半ば上陸したあたりで、狼煙(のろし)をあげさせた。
上陸では、この合図を待っていた。かれらは土嚢の壁を一時に断ちきって水を奔流させるとともに戦場へかけた。
竜且とその部隊は、孤軍になった。
ーー韓信は敵の「半渡」に乗じた。
ついに竜且その人を囲んだ。
楚軍の一方をつねに支えてきた勇将の最期としては、みじめであった。
「漢の将軍というだけでは、おさまりますまい」
「それはわかるが、私が斉王になるのはこまる」
「かといってあなた様以外にたれが斉王になります」
「このままでよいではないか」
(よく考えてみると、大望などといっても儚(はかな)いものだ。わしの場合、大がかりな戦をして自分の才能をためしてみたいという甚だ子供っぽいものにすぎなかった)
「わしは一介の書生でいたかった」
「それはうそでしょう」
「いや、半ば本当だ。あとの半ばというのは野心だが、それも自分の異能を世間でためしてみたいということだけだったように思う」
韓信は、真顔でものを言っている。
「痴(たわ)ごとを」
かい生は笑った、
「もうだめだ」
「わしはこのように苦戦している。いつ韓信の援軍がくるかと待ちのぞんでおるのに、口上というのはそれか。自立して王になりたいというのか」
(まずい)
自立どころか、楚について劉邦を一挙に覆すこともできるのである。
「御立腹なさってはなりませぬ」
「わかった」
「韓信に伝えよ。仮王(かおう)などということはけちくさい。なんといっても大丈夫たる者が強斉を屈服させたのだ。遠慮なく真王になれ」
張良と陳平は劉邦の豹変にあきれた。
◎虞姫(ぐき)
項羽のおかしさは、知らない人間に対しては古家の土壁でも掻(か)きおとすような無造作で殺してしまえるのだが、名を知り、顔を知り、一度でも言葉をかわせば別人のように情誼(じょうぎ)があつくなってしまうことであった。…その情愛は劉邦のその配下に対するその比ではなかった。
「いくつだ」
「十四でございます」
「虞(ぐ)よ」
(こどもではないか)
「陛下。ーー」
「陛下にきらわれたくはありません」
「虞よ」
「桃の唇(つぼみ)が陽に向かううちに自然にほころびるように、むすめもほころびを待たねばならぬ」
(この人は、鬼神というではないか)
劉邦は、弱かった。
(あの弱いやつが、なぜわしに屈しないのか)
項羽はふしぎでならない。
項羽のみるところ、劉邦は食物に執着している。
(劉邦のあたまは、わしと戦うよりもおのれの兵を養うことしか考えていない)
ーーいったい、彭越(ほうえつ)とはなんだ。
ーーああいう人間がいるというのは、漢軍の弱点とみていい。
ーー劉邦の配下など、猥雑なものだ。犬がいるかとおもえば虎も狐もいる。寄りあい所帯ではないか。
これにひきかえ項羽の楚軍は項羽の武に対して信仰的な安心感を持つ組織で、一将といえども天下に野心を持つ者はおらず、みがきあげられたような統制のもとに動いている。
ーー補給難こそ項羽の弱点だ。
ーーまたも彭越が梁にあらわれております。
(まさか)
項羽の主力は、糧道を断たれた。
(劉邦め。ーー)
虞姫は先々月の真夏に女になった。…項羽は三十にもなって顔を赤くした。
…早春の芽は風に痛みやすいものだ
「秋になって天が高くなれば、わが寝所に来(こ)よ」
「以後、虞姫を美人とよべ」
「彭越軍は…楚軍が集積していた兵糧(ひょうりょう)を焼きはらった」
ーー裏切って、敵になりおった。
世界を敵味方の黒白でしか分けることができないというのが項羽の性癖で、これに対し劉邦は世界は灰色であり、ときに黒になり、ときに白になるとおもっていた。
ひと月も経つと、楚城の峰の兵は餓えはじめた。
漢城の峰の兵は、血ぶくれするほどに肥(ふと)っている。
(劉邦のやつ、卑怯な。……)
と、項羽はようやく劉邦の魂胆がわかった。
(彭越を王侯にしておくべきだった)
が、劉邦は応じて来ない。
「それでも汝は武人か」
(父を殺すというのか)
劉邦は戦えばかならず負けてきたが、しかし常に身を陣頭にさらし、かつての多くの王侯のように後方にあって士卒だけを前線で戦わせるようなことをしたことがなく、このことが、漢兵が劉邦についてきた理由の大部分だったといえた。
「項欧を圧倒するしかありません」
と、張良がいった。
「わしに出来るか」
「それはもう、十分に。ーー項王の罪をお鳴らしになることです。数えれば十はありましょう」
「項羽、聞け」
「世にお前ほどに悪逆の者がいようか」
劉邦の胸に命中した。
(やった)
(起きあがらねば、全軍が崩れる)
「虞」
「虞姫に沐浴(ゆあみ)させよ」
「楚の酒が」
「風のような。ーー」
「もはや、戦いはあるまい」
飲み干すつど、項羽は虞姫を抱いた。