ブログ blog page
2020.8.30-5
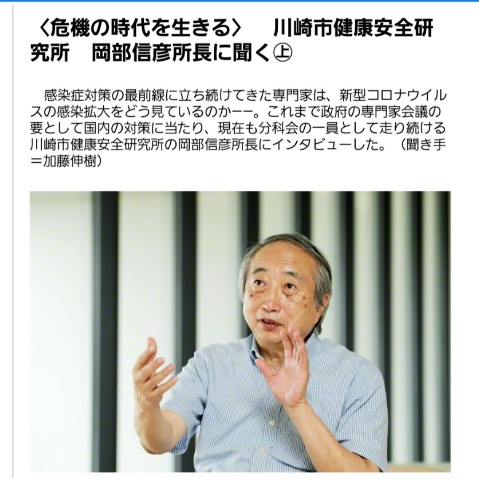
???????????????????????
〈危機の時代を生きる〉
川崎市健康安全研究所 岡部信彦所長に聞く?
●正しい情報見極め「正しく恐れる」
――メディアでは連日、各地の新型コロナウイルス感染症(COVID―19)の感染者数を報じており、その増減に一喜一憂する人もいます。
この感染症が一般にも知られてきたのは、2月から3月くらいのことです。その時は“未知のウイルス”でしたが、この半年で多くのことが分かってきました。最近の感染者数だけで見れば、緊急事態宣言を出した時を上回った地域もありますが、それを気にする方の多くは2、3月くらいの分からない状況のままで、数字が増えていると感じているのではないでしょうか。もちろん、数が増えるのは好ましくありませんが、この間、疫学情報や検査体制の拡充、診断方法の精度の向上、集団感染の調査、診療の経験とノウハウなどが積み重ねられていますし、無症状感染者をはじめ、これまで分からなかった人の感染も把握できるようになりました。そうした数も含まれていることに目を向けないと、「正しく恐れる」の「正しく」が抜け、いつまでも「恐れる」ということになってしまうと思います。
また今、数として報じられているのは、その日の検査で感染が分かった人数です。集団感染が疑われる人を大勢検査すると数も増えますが、これは、あくまで検査した日であり、“その日に感染者が急増、あるいは減少した”ことを指すわけではありません。感染者の増減を正しく理解するには、感染者がいつ発症したのかを見る必要がありますが、この発症日ごとで見ると、日本での7〜8月の増え方は、いわば高止まりのような状況で、一部では微減傾向になっていることも分かります。
――ほかに分かってきたことは、何でしょうか。
世界的にも10代以下の子どもたちの感染者数は明らかに少なく、高齢になるほど重症化率、致死率が高くなることから、この感染症は目下、“大人の病気”と言えます。また高齢者でも糖尿病や腎臓病などの基礎疾患のある方が重症化しやすい一方、発症者の約8割の方は軽症で済むことや“発症した人の約8割は他人に感染させていない”ということも分かっています。
「3密」回避やマスク着用などの基本が命
――どういう状況で広がっているのでしょうか。
最近は会食や職場、家族など、さまざまな状況が挙げられていますが、共通した条件としては、換気の悪い密閉空間に多くの人が密集し、密接して大きな声で会話したり、歌を歌ったりすることで感染が広がっています。ここから「3密」という言葉が生まれましたが、この「3密」が回避されない時に感染が広がっています。また、そのような状況下で手洗いやマスク着用などの対策が行われないと、感染リスクが高まることも分かっています。
――やはり、「3密」の回避や手洗いといった基本が大事ですね。
そうです。私は毎年、インフルエンザの流行時期には“人混みに出る時は注意し”“くしゃみや咳が出る時はマスクを着け”“帰宅したら手を洗いましょう”と呼び掛けています。「3密」という言葉自体は今回の対策で出たものですが、感染症対策の基本は変わっていません。ただ取り巻く環境は、時代とともに変化してきていると感じます。
――どんな変化があったのでしょうか。
特に大きいのが、人の動きと情報量の変化です。
新型インフルエンザが流行した2009年ごろ、海外からの訪日客は年間で1000万人を下回っていましたが、新型コロナウイルスが流行する前には3000万人を超えていました。
情報量については、SARS(重症急性呼吸器症候群)が問題となった03年に比べ、09年の新型インフルエンザの時には、多くの人がインターネットで情報を得るようになり、メールで情報交換することが普及してきました。そこから10年以上が経過し、今では多くの人がSNSで既成メディア以外の情報を目にし、自らも広く情報発信できるようになりました。そこで個人の見解を述べることは自由ですが、それが全て正しい情報とは限らないので、一人一人には、どれが正しい情報かを見極める力が求められています。
また、そうした力はマスコミの側には一層、求められています。出回っている情報の中で何が真実かを見極め、専門家の意見などを踏まえて報道していくことが大切です。
――報道の中には、PCR検査について、“やみくもに行うことを是”とするものもあると感じます。
PCR検査は私の研究所でも毎日行っていますが、今日やって陰性だとすると、それは「今は陰性です」ということしか言えず、明日やると陽性となるかもしれない。また、もし検査で陰性となった人が“感染していないから”と油断した行動を取ってしまえば、逆に感染を広げるリスクがある。「それなら毎日やればいい」と言う人がいるかもしれませんが、そうなっては、きりがありません。
PCR検査はウイルスそのものではなく、ウイルスの遺伝子の一部があるかどうかを調べるものですが、たとえ壊れたウイルスのかけらが少し体内にあるだけでも陽性になります。壊れていれば感染力はありませんが、それでも陽性になるのです。だから、やみくもに検査してしまうと、既に他人に感染させる心配のない人が陽性として隔離されてしまったり、不当な差別を受けてしまったりするなど、誤った行為につながる可能性もあるのです。
そもそも日本の検査の精度は高く、数個のウイルス遺伝子があるだけで陽性になります。数百という遺伝子がないと感知できないものを使用する国もあります。そうした精度の違いを見ずに、日本も海外と同様に大々的な検査を行政が担うとすると、技術的にも費用的にも、効率性からも無理があると思うのです。