ブログ blog page
誰もかれもが堪忍のしくらべ
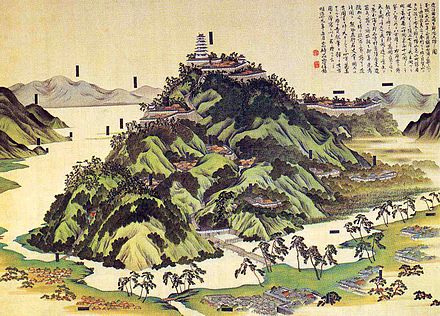
◎再び雌雄
「ーー信忠、もうよかろう。おぬしに家督を譲ってな、わしは近江へ新城を築いて移る」
この話を伝え聞いて、家康はさっそく人夫と石材を送ってその築城を助けた。
信長が何のために岐阜城を信忠に譲って、安土へ移ろうと考えたかが、はっきりと分かるからであった。
「なるほど、明智どのの墨縄、丹羽どのの奉行か。それではその間にこっちも作佐に墨縄とらして、少しばかり城普請のまねごとでもいたそうかの」
家康はそう言って表面は笑っていたが、いよいよ心を締めて信長に当たらねば……と思うのだった。
「いままで、天下に号令した者で、京におって天子にご迷惑をかけなんだ者はひとりもない。藤原、平氏、北条、足利みな天子のお膝もとにあって倒れるときには塁を天子に及ぼしている。それをはっきり気づかれている信長どのゆえ、安土の次にいよいよ天下へ号令するとなったら、たぶん、いま石山本願寺にある大阪の地あたりを選んで城を築こうて」
「その織田どのが、いよいよ天下を握る時節は到来と、安土へ居城をすすめてゆく。よいかの、織田どのを疑うのではないぞ。もし万が一、援軍の来ぬ場合、……いや、その織田勢がもし敵に廻った場合……そのときにも崩れぬ用意がわれらにあるか……」
家康の観察によれば、古来から現在まで、戦に負けた方が滅んでゆくのは当然ながら、勝った方もまた、遠からず必ず破滅を掴みとっているのであった。
勝利と有頂天とは避けがたい人間の習癖らしい。
その眼で見ると、家康には、信長もまた勝ちすぎたような気がしてならなかった。
勝つとおごる。おごるとは横暴の別語、武田勝頼の今度の敗因は高天神の戦に負けた勝ったときに芽生えていた。その同じ芽がもし家康の内部にあってはと、家康は勝利の日から残酷なほど冷静に自分の実力の計算にかかっていたのだ。
信長はその反対だった。
勝ちに乗じて、一挙に天下布武を遂げようとしだしている。
「おお鬼の子め、よくぞやった。そなたの性根、信長生涯忘れまいぞ。よいか、褒美にわが名の信をつかわす。今日からは貞昌を信昌と改めよ」
しかし、信長のそうした態度のうちには、家康をはばかる気配は完全に消え失せてしまっていた。
(実力で、いつか家康を押さえて来る)
生涯決して主は持つまいと心に決している家康。それをよく知っていて、三河の親類と呼んでいた信長だったが、やがて一人の命令者として家康の上に君臨して来そうな気がしたのはそのときからだった。
「人間はの、勝ったときに、なぜ勝ったかを調べ忘れる。……こんどの勝因の第一は、そちたちの律儀な武勇であった。何ごとにもわしを立て、上下一つになって一糸もみだれぬこの強さ……そちたちの並なみならぬ律儀な武勇がなかったら、織田どのはただ見捨てるだけではなくわれらを攻め滅ぼしていたであろう。援けて何の利益もないのだからの……第二の勝因は運であった。運は寝て待ってよいものではない。わしが、わが結ぶべき相手は武田にあらず、北条にあらずとさとり、境を接した織田どのと結んだことに運があった。遠交近攻の考え方からすれば……しかしその運は将来も、われらにつきまとうていると思うてはならぬ。そこでわしは、わしの行くべき道、歩くべき策をこう考えた……」
……まだ家康が勝ち足りないのであろうか。
「わしはこれから、どんなに敵を迎えても織田どのの援けをからずに済むだけの地力を持たねばならぬとのう。その地力を持ったときに、運はまたわしに笑顔を向けようで。それまでは危い戦は一切さける。勢いに乗ずる代わりに、家臣の中へ、わが眼が届かず、埋もれてある者はないか。八十万石足らずのわずかの領地じゃ。隅々まで心して眼をとどかせ、みなが裕福になるよう神仏に誓って努めてゆこうとのう」
「三方ケ原(みかたけはら)のときはひどくお違いなされたものだ」
「いかにも、あのときには、負け戦のあとであったが、ハチ切れそうな勇ましさ、ところがこんどは、おそばにいても息がつまる」
「いや、これがお館のご用心じゃ。近ごろはここであのような書きものをなさるか、馬に乗って村々を歩き、百姓の誰彼に話しかけて歩くのが仕事のようじゃ」
「領民を富ましておけば、いざというときに八十万石が、百万石にも、百二十万石もの力を出すからの」
「お愛……」
……
「こなたに子供ができたら、どのような子が産まれて来るであろうかの」
「さあ……お心に添うような賢(さか)しいお子は」
「産まれて来ぬと思うのか。わしはそうは思わん。ひどく几帳面な子になるかも知れぬの」
「お側にほかの女子を差し上げとう存じまする」
「お館さま、愛は身ごもったような気がいたします。それでお願いいたしました」
一夫多妻のこの時代には、身ごもるとほかの女性を枕席(ちんせき)へ差し出すのが女の心得の一つであった。
「は……はい。それに、もう一つ、若御台さまに、二の姫がお生まれでございました」
「徳姫が何としたのだ」
「このまますぐにご実家へ帰ると……」
(若さというのはそのように無分別なものであったろうか……?)
「その僧侶を斬り捨てたのか?」
「やはり、殺めたのだな、困ったものだ」
「これからはの、しばらくは誰もかれもが堪忍のしくらべじゃ。堪忍ほどわが身をまもってくれるよい楯はない。わかるかの、誰にもできる堪忍のことではないぞ。誰にもできないほどの堪忍を、じっと育ててゆかねばならぬぞ」