ブログ blog page
初対面で自分の長所を
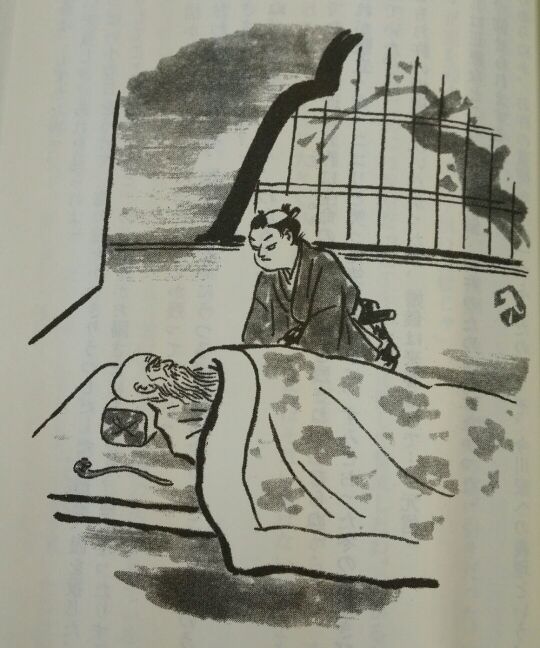
◎歩速の諧調
「妻子を忘れて大局を睨みまする。元信が郎党とともに斬り死にして、それが不殺のまことにかないまするならば潔く斬り死にする。が、その反対と見てとったら、たとえ御所の命なりと、断乎これをしりぞけまする!」
「たわけめッ!」
……
「思いあがった高慢者めッ、いま一度申してみよ」
「はい。何度でも申しまする。たとえ御所の命なりと……」
「短気を起こすな。短気は人を盲にするぞ」
◎薄陽
「許して下さりませ元信さま……鶴はきっとよい妻になりまする」
(弱者はつねにみじめなものだ……)
氏真ずれが弄んで捨てた女を妻にする。
(肩の荷は思いほどがよい。お許はそれを背負いきれる男なのだ……)
◎不如帰(ほととぎす)
「これこれ針売り、その方の生まれ年は猿年であろうが」
……
「いかにも拙者は申の年じゃが、おぬしは午年じゃな」
「ーーこの世は力なのだ」
「ーー力ある者は、いつでもわしの手から奪うがよい」
「濃!」
「おれはしばらくそなたを遠ざけようと思う」
……
「そなたは産まず女(め)、わしは側女(そばめ)を持とうと思う」
「いつかはな、義竜め……よいか、忍べよ」
◎信長構図
(あやつ、きっとまだいよう)
「では、猿とお呼び下され!」
「そなた子が産めるか」
「ひとりでは産めませぬ」
「深雪に、お類に、お菜々でござりまするか」
「この猿は、松下嘉平次がもとでは、木下藤吉郎と申していました」
「それゆえ噂、流言は勝手でござろう……」
(そうだ! 今川義元の背後をおびやかす手は越後にあった……)
「いつかわしの片腕になる……奴かも知れぬ」
「人と人とはな、はじめはみな初対面じゃ。兄弟でも父子でも」
.……
「が、初対面で自分の長所を相手にさとらせる術を知らぬ者では役に立たぬ。あやつはな……」
……
◎帰雁(きがん)の宿
姫は月足らずで生まれたが、それが他人の子であろうなどという噂ではなかった。その反対に、両親が婚礼以前、すでに交わりがあったのでは……という噂であった。
(わしのような者を……)
そう思い、どんな艱難に耐えても、この人々の心の柱にならねばならぬとも思った。
(宿なし大名か……このわしは……)
(哀れなのはわしだけではない……)
(祖父に似ていすぎる……)
短気でなければ猛気のために、身をやぶるおそれが十分に感じられた。深い洞察力を持っていながら、カーッと燃えあがる血潮のために、身を誤りそうな危険が。
次郎三郎は何か見えないものに圧倒されて、ここでは自分が消えてしないそうな気がしているのだ。……自分の祖先たちが、何をのぞみ、何にたよって、このような七堂伽藍を営んだのか……その精神の奥の奥にあるものが、まだ彼には見当もつかなかった。
(いったいこの結構はなんであろうか……?)
心にともった一点の火ーー
わが身のふがいなさ。
家臣の哀れさ。
それにもう一つ、ここで見聞することはすべて駿府で聞くよりも祖母の遺言と雪斎長老の公案に強いひびきでつながった。
「殿はの、殿のうしろに、家臣の粒々辛苦がかくされていることをお忘れなさるまいぞ」
「まず銭を積み、武具を備え、次には糧食をととのえる。これはみな殿初陣の用意でござる」
「爺……次郎三郎は、よい家人をもって仕合わせじゃ。父祖のおかげ……このとおりじゃ……爺……」
◎闌鶯(らんおう)の城
「もし御所さまお疑いならば、ご上洛に先だって、元康が心、お試し遊ばせませ」
この夫婦の交わりは世の常のそれよりはるかに濃かったゆえかも知れない。
「いま、日本中で、こうして女子供ばかりで歩けるところは駿府以外にないそうな」
駿府と三河の女性の相違。
一方はどこまでもつつましく堅実なのに、駿府の女子はみなりの派手さに加えてことごとに表向きの事にまで口を出した。